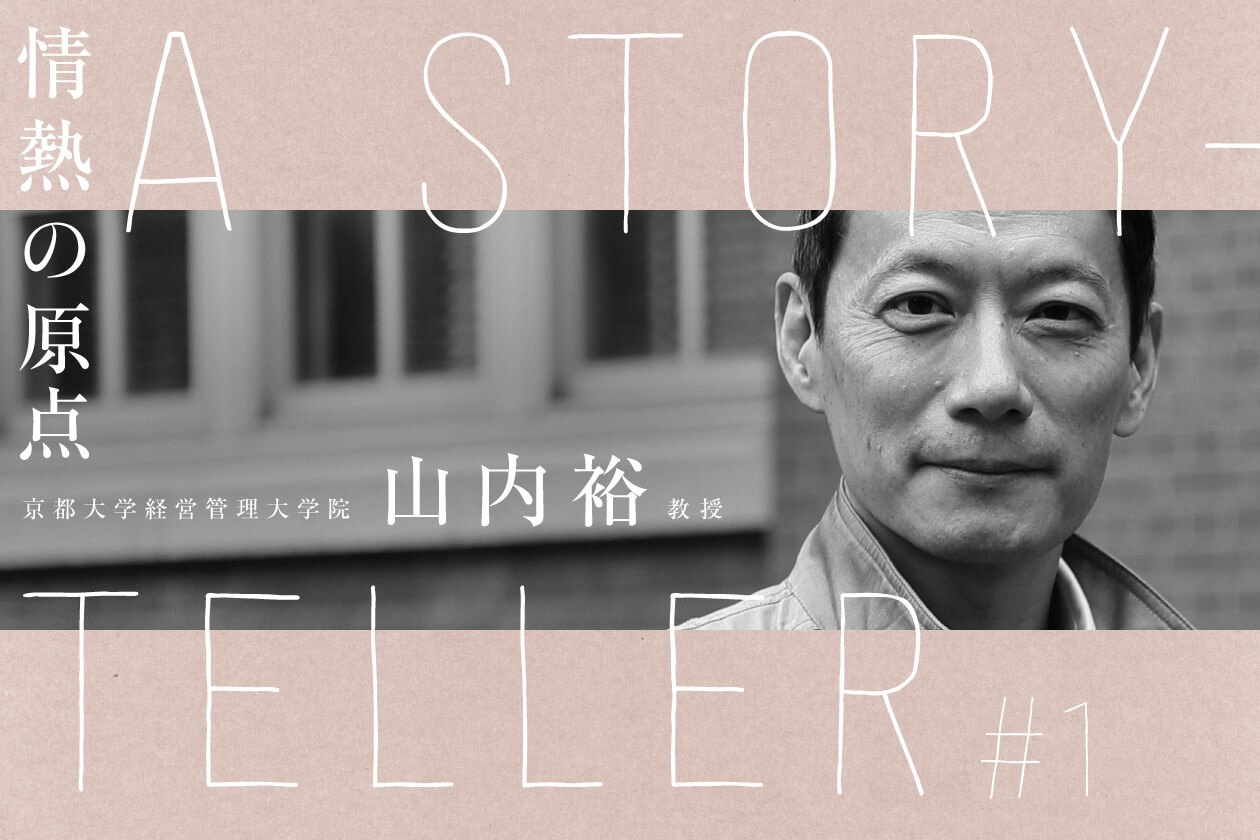a storyteller ~情熱の原点~ 第6回 NPO法人「数学カフェ」代表理事 根上春氏
数学を学ぶ楽しさがつなぐ共感の輪――“誰もが幸せに生きられる”社会を目指して

さまざまな分野で意欲的に挑戦を続けるイノベーターたち。革新を起こし時代をリードする彼らを突き動かす、その原動力や原体験とは一体何なのだろうか――。その核心に迫る「a storyteller~情熱の原点~」。第6回は、数学カフェの代表である根上春氏に話を聞く。高校生のときに数学に魅了され、2015年に数学を学びたい人が集まるコミュニティ「数学カフェ」を立ち上げた。小学生からシニアまで数学を好きな人が交流しながら学ぶ場を運営すると同時に、地方でのセミナーやワークショップを通じて地域の教育格差の解消にも挑む。数学によって、誰もが幸せに生きられる社会をつくりたいと考える、根上氏の活動の原点を追った。
「証明」問題の精読から生まれた数学への情熱
――まずは根上さんが今、どのような活動をされているのかを教えてください。
根上2015年に任意団体として「数学カフェ」を立ち上げ、2021年にNPO法人化しました。主な活動は3つあります。1つ目は、オンラインとリアルの両方で数学の専門家による講演や参加者同士の交流イベントを行う活動です。数学カフェのスタート時は数学の研究者による専門的な内容でした。しかし、教室がいっぱいになるほど参加者が集まり、「数学が好きな人や、社会に出た後も数学を学ぶ気持ちを持つ人がこんなにたくさんいるんだ!」と驚きました。最近は、より広く数学の魅力に触れてほしいという趣旨から「高校で学ぶ『シグマ』って何だろう?」から始める予習会を設けて、さまざまな方が専門家の講演を楽しめるようにしています。
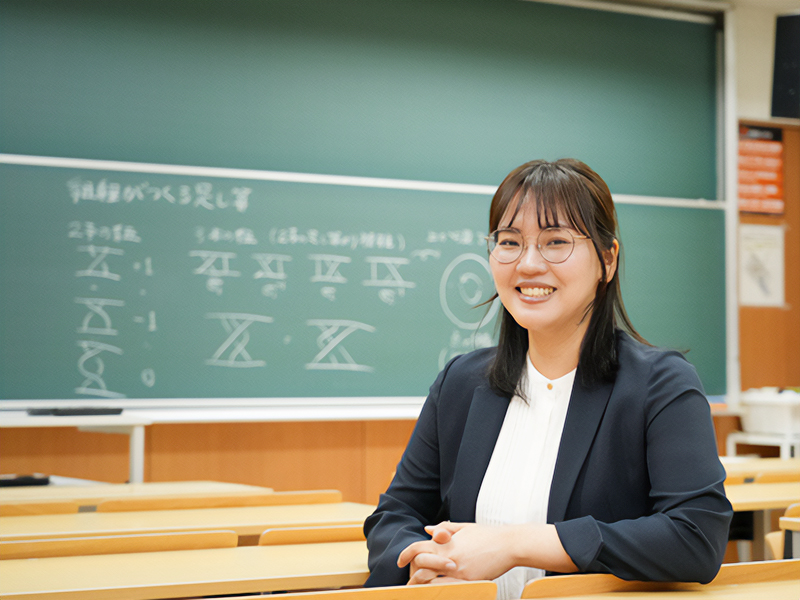
根上春氏
2つ目は、地域間の教育格差を解消するための数学ワークショップの実施です。現在は数学カフェのメンバーとつながりのある沖縄県や熊本県を中心に取り組みを継続しています。主な参加者は中学生や高校生ですが、年齢を問わずに多くの方が参加しています。
3つ目が、オンラインで実施している「もくもく会」です。みんなで集まってもくもくと勉強するというのが名前の由来です。例えば、講演会やワークショップに参加してモチベーションが高まった後は、勉強の継続が課題になります。そこで、もくもく会では平日の夜に有志が毎日集まり、勉強内容を共有することで学び続ける環境を提供しています。
――根上さんが数学を好きになったきっかけは何だったのでしょうか?
根上子どもの頃、算数や数学という言葉を知らないときからもののカタチが好きだなと思っていました。本格的に数学を好きになったのは高校生のときです。試験の成績がすごく悪かったんですよ。「なんでこんなに悪いんだろう」と悩み、勉強方法を見直す必要があると感じました。
まずは先生の進めるペースを一旦無視して、証明問題の問題文を、自分が完全に解るまで丁寧に読むようにしました。ときには、問題文のはるか前のところまで戻りながら納得が行くまで何度も読んで自分の言葉で説明しようとするうちに、問題文の1行1行に「こんなに深い意味が込められているんだ」と理解できました。そうしたら、(それまで数学は成績が悪かったのに)証明問題が解けるようになり、もっと他の解き方はできないかと考えてみたら、自分なりの証明方法を見つけることができるようになって、数学が楽しくなりました。
数学の問題の新しい解き方を見つけることは、その問題を説明する「新しい言葉を創り出す(言語化する)」ということでもあります。分からなかったことを、じっくり考え、自分の力で新しい解釈や解法を生み出していく過程が、どんどん面白くなり、自分のアイデアを発揮できる面白さが加わってますます数学が好きになりました。
――高校生のときから数学を職業にしたいと考えていたのでしょうか?

根上いいえ。数学を職業にするという選択肢は、当時はまったくありませんでした。国家資格に魅力を感じ、大学は薬学部に進みました。学び始めると薬学のアプローチが「自分にはあまり合わないな」と感じたんです。将来が定まらずにいろいろな勉強をしたのですが、その中でもやはり数学が一番面白かったですね。自分が好きなのは数学だなと思い、薬学部から数学科へ転学しようと考えました。
でも、周囲からは猛反対されましたね。特に母からは「それ以上理屈っぽくなってどうするの!」と言われ、受け入れてもらえませんでした……。学費を出してもらう両親にそこまで反対されたら難しいなと思い、薬学部にいながら数学を勉強できる方法を模索しました。修士課程では創薬と機械学習、グラフ理論などを組み合わせた研究を行いました。
独学でも数学を勉強しようとした際、最初に手に取った線形代数(※)の本がものすごく難しく、1ページ目の前半を読んだだけで挫折してしまいました。「なんだこれ!」とショックを受けましたが、その本は難解で有名だったようです。知人からそのときの自分に合った本を教えてもらいました。その経験から「違う分野を専門にしているけど数学を勉強したい」と考える人や、「学校の授業では苦手だったけれど、改めて数学を勉強し直したい」と考える人をサポートできる場所があればいいなと考えたことが数学カフェを始めたきっかけの1つです。
- ※線形代数:線形空間と線形変換を中心とした理論を研究する数学の一分野。主に行列やベクトルを扱い、幅広い分野に応用されている
一歩ずつ積み上げる、数学と信頼の共通点
――数学カフェのスタートから現在までどのように活動を発展させてきたのでしょうか?
根上大学院を修了後、一般企業に就職しましたが、環境が合わず退職し、エンジニアの仕事をしながら過ごしていました。そうした中で「数学の話ができる知り合いがほしいな」と思い、Facebookで数学イベントへの参加者を募ったのが数学カフェの始まりです。最初は4人でしたが、2回目には10人になり、あっという間に参加者が増えていきました。
全国に数学愛好者が集まる団体がたくさんある中で、「自分たちの特色を打ち出すにはどうすればいいか」を考えたときに予習会なども実施し、真剣に数学を学べる場にしていきたいと考えたんです。自分自身、もっと勉強したいという意欲が増していったので、セミナーでは研究者を招いて長時間みっちり話していただくようなものを企画しました。
講演会には北海道や九州から来てくださる人もいて、「地方でも開催してほしい」という声もいただくようになりました。こうした活動の中で、BIPROGY総合技術研究所の川辺治之さんともつながりが生まれ、活動の輪が広がっていきました(参考「研究員と会える! 話せる!「R&D Meetup Days 2024」開催」)。
同時に「数学カフェとして地域間の教育の格差や男女差、ライフスタイルの変化に取り組みが対応しきれていない」と感じ始めていました。この頃、すうがくぶんか社さまから支援いただき、2021年に法人化に踏み切りました。コロナ禍では講演やワークショップをオンラインに切り替えました。そこで分かったのは、オンラインだから地方の人が参加するかというと、そうではないということ。地方に情報が届きづらいという課題も見えてきました。

――地域間の教育格差解消を視野に入れた活動の拡大に向けて、どのような工夫をされていますか?
根上地方との関わりが増えていく中で、多くの地域に数学に対する熱意を持つ方がいることが分かりました。自分1人では限界があるので、そういう方々と一緒に全国に向けて数学の楽しさを知ってもらう取り組みを拡大させたいと考えています。ネットワークを広げるためには、信頼を獲得することが大切です。いきなり訪ねて行って「やりましょう!」と言ってもうまくいきません。
数学は、1行を理解することが非常に難しい学問です。有名な数学者の先生でさえ、数学書を読むのに1日に1行しか進まないとおっしゃる方もいらっしゃいます。逆に言えば、たった1行のわずかな進歩がとても大きく、意味があるということです。
この考えをベースにすると、信頼を獲得するのも一歩一歩で、やはり時間がかかるものです。最初は伝わらなくても腐ったり落ち込んだりしない。自分が行動することでしか信頼は得られないのだから地道に向き合っていこうと考えています。そのマインドを数学に育ててもらいました。
――セミナーやワークショップなどの活動で印象に残ったエピソードはありますか。
根上慢性疾患でリハビリ中の方がオンラインでセミナーに参加され、以前のように数学の世界で働きたいという意欲が湧いたと言ってくださって、とてもうれしかったですね。オンラインでもセミナー受講可能としたことで、学びたい思いはあるが移動に制約がある(困難が伴う)方に以前より気軽に参加していただけるようになりました。
また、熊本でイベントを開催したときに福岡から駆けつけてくれた小学生がいました。その子は数学がとても好きで「無限」に関する疑問を持っていたんです。親に聞いても分からないからと数学者の先生にその場で質問したところ「すごくいい質問だね。これは大学で勉強するような難しい問題なんだよ」と言って解説してもらえて、とても喜んでいました。
熊本のワークショップではアートや社会、理科など生徒たちが得意なものと数学を組み合わせて課題を考える授業を行い、「楽しい」という感想をいただいています。子どもたちが自らのアイデアを生かし、活躍できる場をつくれていることに喜びを感じています。その他、会社を定年退職して毎日もくもく会に参加されている方もいます。数学カフェを通じて同じ趣味を持つ仲間が増えて生き生きしている姿を見ると私も励みになります。


数学が教えてくれた、好きを貫く幸福論
――数学の社会的応用についてどのようなビジョンをお持ちでしょうか?
根上社会貢献や社会福祉のための数学という視点がもっと広がることが私の希望です。生成AIを活用して多くの人が自由にプログラムを書いたり、高度な数学の知識を検索できたりするようになり、数学のハードルはどんどん下がっています。希少疾患の薬の開発など、これまでマネタイズできないからという理由などで進まなかったものにもっと日の目が当たるといいなと思います。
私も今、目の見えない人が数学を楽しむための教材作りに取り組んでいます。これは単に目が見える人が「支援をする」という一方的なものではなく、目が見える人には分からない、目が見えない人の持つ力を教えてもらっている気がします。このプロジェクトを通じて、きっと新しい数学の学び方を生み出せると確信しています。また、公害や資源の枯渇など短期的な利益追求が社会に害を及ぼすような状況や、倫理的な観点で社会実験が難しいような問題も、数理シミュレーションによってさらなる説得の力を持てるようになればいいなと思います。
――数学教育や数学の普及活動に尽力されています。日本の数学教育の現状についてどのようにお考えでしょうか?
根上日本は数学の成績は国際的に上位ですが、数学が好きな人の数は国際平均をはるかに下回るというデータがあります。数学に対してポジティブな気持ちをもっと育んでもらいたいです。文部科学省の学習指導要領の中には、数学の技術習得だけでなく、数学的活動の楽しさや数学のよさを実感して粘り強く考え、数学を生活や学習に生かそうとする態度を育むという項目もありますが、あまり重点が置かれていないように感じます。数学の問題だけに閉じずに、社会とのつながりの中で数学を考える機会が増えればもっと数学を身近に感じられるようになるのではないでしょうか。
また、大人になってから数学を学ぶ人の割合も日本は少なく、子どもの頃に楽しかった経験があれば、その割合も増えていくのではないかと思います。2024年の12月に海外で開催された女性数学者の集まりに参加しましたが日本は圧倒的に女性が少なかったですね。アメリカ、ニュージーランドの他、最近ではインドでも数学を職業にする女性は増えています。そういった国では女性が活躍するためのサポートも手厚くなります。日本は活躍できるはずの人が活躍できていない、機会のロスがあるのではないかと感じています。
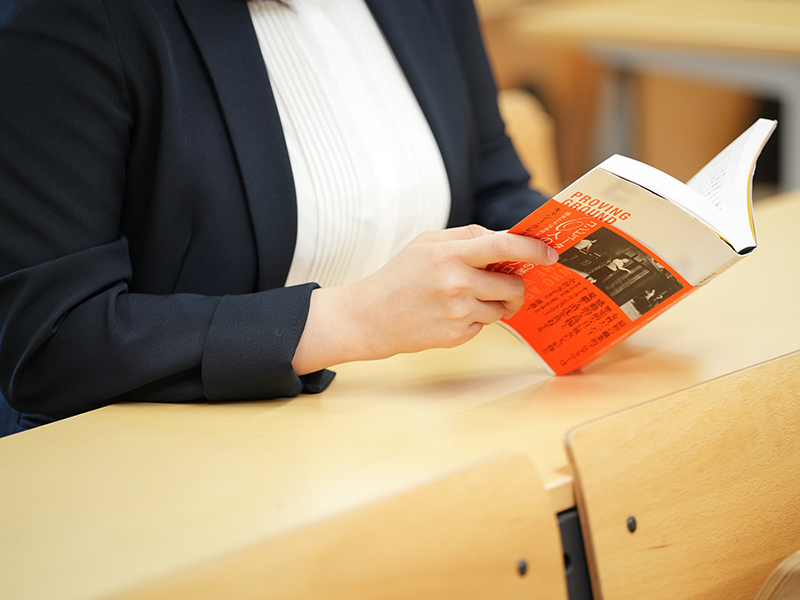
その折、先ほどご紹介した川辺さんをきっかけに、同じくBIPROGYの羽田昭裕さんが翻訳された『コンピューター誕生の歴史に隠れた6人のプログラマー』(キャシー・クレイマン著/共立出版)を手に取る機会がありました。この書籍を読むと、男性が多いイメージのエンジニアの世界でも黎明期から女性たちが活躍していたことが分かり、勇気づけられました。
私自身も、数学に関する活動をできるだけ周囲に発信するようにしています。私が数学の研究や活動をしている姿を見てもらうことで「女性たちの励みになるかもしれない」と考えるようになったからです。
――今後、数学カフェの活動を通じてどんなことに挑戦されていきますか。未来に残したいものや伝えたいメッセージをお聞かせください。
根上一番の目標は、境界なくいろいろな人が自分らしく、楽しく暮らせる場をつくることです。社会を変えていくには、活動を引き上げてくれる人や当事者として打破してくれる人の力が必要です。自分自身がその一翼を担えたらと思っています。数年前からガーナの女性数学者とやりとりをしており、コラボレーションをする予定です。国境を越えて教育の格差を解消するような活動もしていきたいですね。誰もが生まれや社会的な不平等によらず、幸せに生きられる社会をつくりたい――。その手段が、私にとってはたまたま数学でした。最初は、数学の道に進むことを周囲からは反対されましたし、「変わった人」という扱いもされました。
それでも、私は数学が大好きです。数学に向き合っていると本当にワクワクするんです。それが活動の原動力です。自分の好きなことをしていると、こんなにも幸せになれるということを数学が教えてくれました。これからもこの気持ちは変わらないと思います。

プロフィール
- 根上春(ねがみはる)
- 東京大学薬学部を経て、現在は千葉大学大学院博士後期課程にて「組み紐」と「微分方程式」をつなぐ研究に従事。薬学から数学に転向した経験を生かし、誰もが数学を楽しめる空間を目指したNPO法人「数学カフェ」の代表理事として活動中。沖縄タイムスの教育面エッセイ執筆や沖縄県内教育雑誌『ジュクタン』での連載の他、熊本県での教育支援活動を通じ、大都市圏外でも数学アウトリーチの可能性を日々探求している。