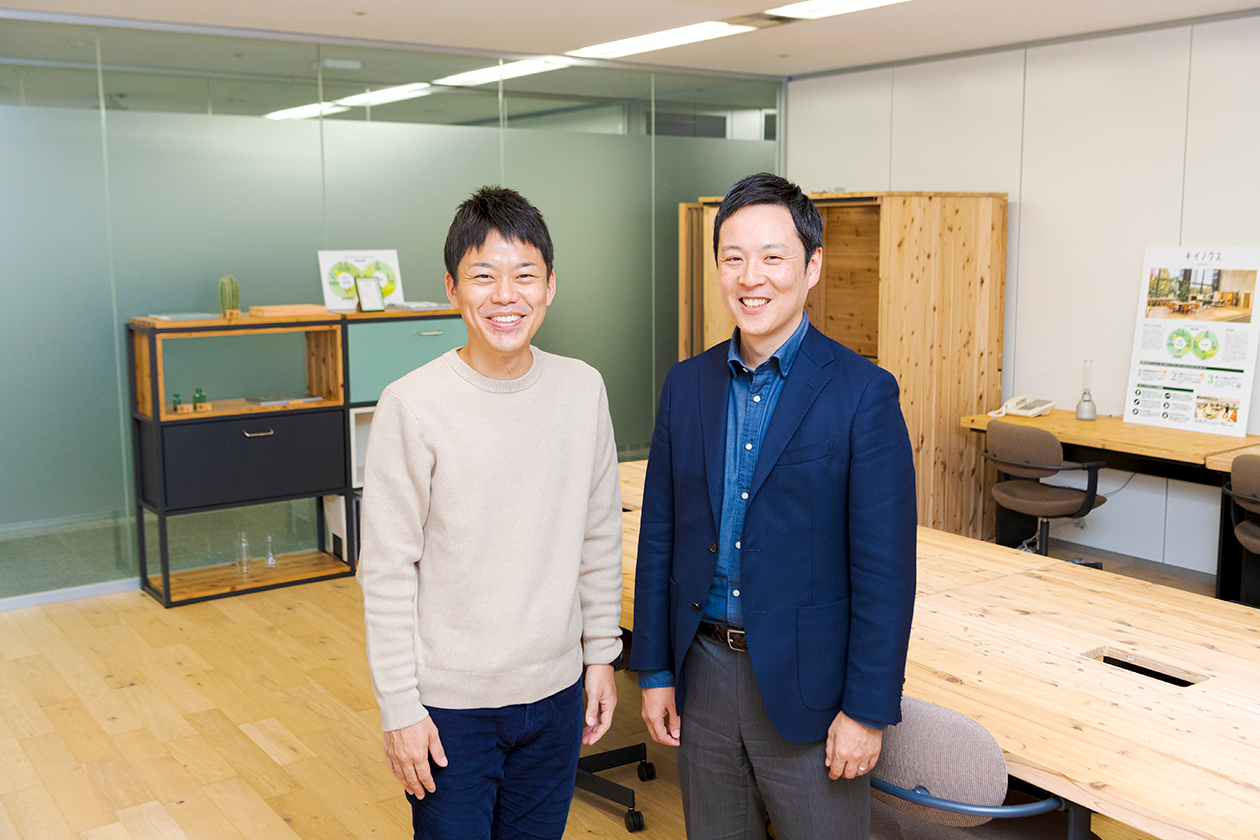男性育休がもたらす組織風土改革と家族の絆──育休を取得した組織長とお客さまの座談会
連載「パパ育休を本音で語り合おう。仕事、組織、家族の実際のところ」第3回

2022年10月から「産後パパ育休(出生時育児休業)」の制度が始まり、2025年4月からは出生後休業支援給付金が開始されるなど、男性の育休取得推進に向けた法整備が進んでいます。BIPROGYでは2024年度よりマテリアリティとして男性育休についてのKPIを掲げ、取得推進に取り組んでいます。今回は、男性の育休取得が組織内外にもたらす影響について、育休を取得したBIPROGYの組織長と顧客である農林中央金庫および農中情報システムの管理者が語り合いました。
育休取得を目指し、チームで入念に事前準備
――まずは自己紹介をお願いします。
松浦2004年にBIPROGY(当時日本ユニシス)へ入社し、営業として金融機関のお客さまを担当、現在はサービスイノベーション事業部の部長を務めています。2024年5月から1カ月間育休を取った際は、農林中央金庫さまの基幹系システムを担当しており、営業チームリーダーでした。今回、対談させていただく渡邊さんとは2024年に実施した銀行の預金や為替を扱う勘定系システムのクラウド化プロジェクトからのお付き合いです。涌井さんとは2016年に始まった勘定系システム再構築プロジェクトからのお付き合いになります。

部長 松浦祐太
渡邊農林中央金庫で勘定系システムの企画を担当しています。松浦さんとは勘定系システムのクラウド化対応ということで約1年半、一緒に業務をさせていただきました。松浦さんはいつもポジティブなレスポンスをくれる心強い存在です。

部長代理 渡邊雄樹氏
涌井農中情報システムで勘定系システムのシステム基盤にかかる設計・開発を担当しています。松浦さんとは2020年に稼働を迎えた勘定系システムで4年間開発をともにしました。松浦さんは責任範囲が増えて、どんどん頼もしくなっていきました。

プリンシパル 涌井浩二氏
――松浦さんが育休を取得したきっかけを教えてください。
松浦妻と話し合い、出産直後で彼女の体が一番つらい時期に育休を取ることに決めました。ただ、プロジェクトが佳境だったことや、私に「仕事を頑張ってほしい」と妻が思っていることもあり、半年や一年間などではなく、1カ月間の取得にしました。
――組織長としてどのように準備されたのでしょうか。
松浦安定期に入ってからまず上司に伝え、メンバーには育休に入る2~3カ月前に伝えました。育休中の対応に関しては、マネジメント業務は上司にお願いし、実務はメンバーと細かく話し合いをしました。メンバーが自主的にどう対処するかを考え、話し合ってくれて、頼もしかったです。渡邊さんと涌井さんには育休取得の1カ月前に1カ月間休むことをお話ししました。
渡邊2024年7月に勘定系システムのリリースを控えていたので、最初は不安でしたね。通常のシステム更改だけでなく、2024年5月に施行された経済安全保障推進法が当システムに適用されることが決まっていたからです。そのため、関係するベンダーさんや協力会社さんへの情報提供依頼や取りまとめなど、さまざまな対応が必要なタイミングでした。
涌井5月から経済安全保障推進法への審査提出が始まり、そこからシステムリリースまで2カ月しかありませんでした。もし審査が通らなければ、システムリリースが延期になってしまい、大幅なスケジュールの見直しや新たなコストが発生する恐れがありました。そういった状況下において、松浦さんが不在になることに焦りはありました。
ただ、チームメンバーである後輩の方が対応する機会を増やし、1~2カ月かけてしっかりと準備をしてくれました。結果、松浦さんの業務を後輩の方が引き継いで、スムーズにプロジェクトが進行しました。松浦さんがいないことで精神面での不安はありましたが、松浦さんの上司の方がフォローしてくれたこともあり、問題なくシステムリリースを迎えることができました。
松浦後輩は30代前半の中堅社員です。経済安全保障推進法への対応は、BIPROGYにとっても乗り越えなければならない壁だったので、社内にはチームメンバー以外にもサポートしてくれる関連部署の方たちがいました。今まで裏方として動いていただいていたこういった部署の皆さまにもお客さまとの会議に出席してもらうなどして、万全の体制を整えました。
後輩は「チームリーダーが不在になることに不安はあった。でも、育児に対する考えや各メンバーに担ってほしい役割、期待値を早くから共有してくれたことで、業務の準備を万全に整える期間を確保できたし、気持ちを整理する時間も持てた。だからこそ、自分の成長に生かそうと前向きなマインドになれた。結果、組織として強くなれたと思う」と話してくれました。
部下が成長し、組織が強くなった
――育休中はどのように過ごしましたか。
松浦授乳以外の育児と家事は「すべて自分が引き受ける」という意気込みで育休に入りました。ただ、夜泣きは授乳しないと治まらないことも多いので、妻に頼る場面が多かったですね。この経験もあり、妻の負担をどれだけ軽くできたかはなんとも言えないのですが、私と一緒に育児のスタートを切れたのが良かったと妻は言います。「出産後、思うように動けなかったり、体の変化に不安を感じたりする中、一緒にいてくれて精神的にも助かった」とも言っていましたね。子育ての大変さと楽しさを妻と共有できて絆が深まりました。

――育児による気づきはありましたか。
松浦仕事と子育てには、多くの共通点があると感じました。子どもの成長の過程は、仕事でスキルや知識を習得して目標達成に向かう点と似ています。
例えば、子どもを育てる上で、家は「ここにいてよいのだ」と思える安全な場所であることが大事です。安心安全な場所で自己肯定感を育むことで、興味を持ったことに挑戦するマインドが生まれます。これはチームビルディングにおいて心理的安全性を担保することと同じだと思いました。
ほかにも、成功談ばかりでなく失敗談を伝えたり、子どもの意思決定に介入し過ぎたりしないことも、組織運営やメンバーへの接し方と共通するポイントだと感じました。
自分自身の変化としては、子どもは予測不可能な行動を取るので、寛容さや柔軟性が増したかもしれません。
渡邊私は妻に育児を任せっきりだったので、松浦さんの感想を新鮮な気持ちで聞いています。我々が携わるシステムの開発には担当業務に関する知識だけでなく、いろいろな経験を踏まえ、新しいものを作っていくということが求められていると思います。視野が広がり、多くの気づきを得る育児経験は貴重で、こういう意味でも男性が育休を取得するのは良いことだと思います。
涌井松浦さんが育休で不在になったことで、後輩の方が急激に成長し、組織として厚みが出たと感じます。育休中に、自分の仕事が奪われてしまうのではないかと恐怖心が芽生えることはあるのかも知れません。しかし、新しいチャレンジができる機会だと前向きに捉える時代になったのではないかと思います。松浦さんの仕事を後輩の方が引き継いだことで、松浦さんは復帰後に新しいプロジェクトにチャレンジしています。
松浦仕事を任せることで組織が成長するのを、身をもって実感できました。組織長としてメンバー一人ひとりが活躍できる場を作ることが大事だと感じています。組織が成長したので、自分もさらにチャレンジしていこうと前向きな気持ちが生まれました。
育休は組織や部下、リーダー自身の成長の機会と捉えてほしい
――男性育休が社会に浸透していく中で、取引先に望むことはありますか。
渡邊業務を進めていく上で今後ますます多様な視点が必要になってくると思います。男性育休だけでなく、多様な経験ができる環境づくりに取り組んでいる企業とお付き合いしていきたいですし、我々もそうありたいと思います。
涌井農中情報システムは厚生労働省の「プラチナくるみんマーク」を取得しました。育休を取得する男性社員が増え、育休を取得しやすい雰囲気が社内に根付きつつあります。BIPROGYや当社のような形で、会社には育休を取得する社員をサポートする体制づくりが必要だと思いますし、社会全体も男性育休の促進を理解し、協力していくべきと考えます。仕事は代われる人がいますが、子どもの親を代われる人はいませんから。
――育休取得を考える男性に向けてメッセージをお願いします。
松浦育休は、タイミングは人それぞれですが、事故や急な病気などとは違ってある程度前もって準備ができる長期休暇です。チームで準備して乗り越えることで、組織が強くなります。組織長が不在になることでメンバーに負担がかかることはありますが、メンバーの成長の機会だと前向きに捉えてほしいです。育児以外にもさまざまな事情によって、休みが必要になるケースはあるでしょう。そういったことを想定してチーム運営を考えることは、組織長自身の成長の機会にもなります。個人の価値観やライフスタイルを尊重し、多様な選択肢のある組織になることが理想だと思います。