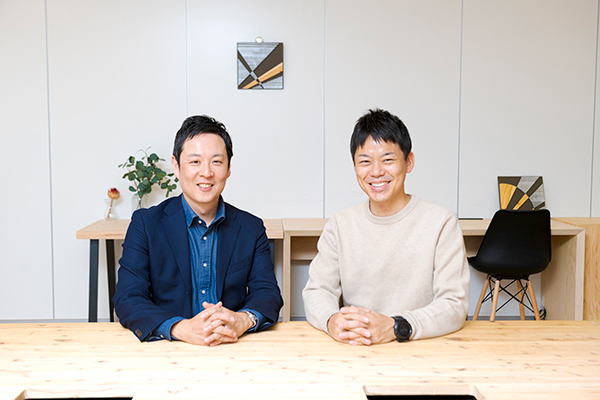男性育休がもたらす組織風土変革と家族の絆──イクボスと育休取得社員による対談
連載「パパ育休を本音で語り合おう。仕事、組織、家族の実際のところ」第2回
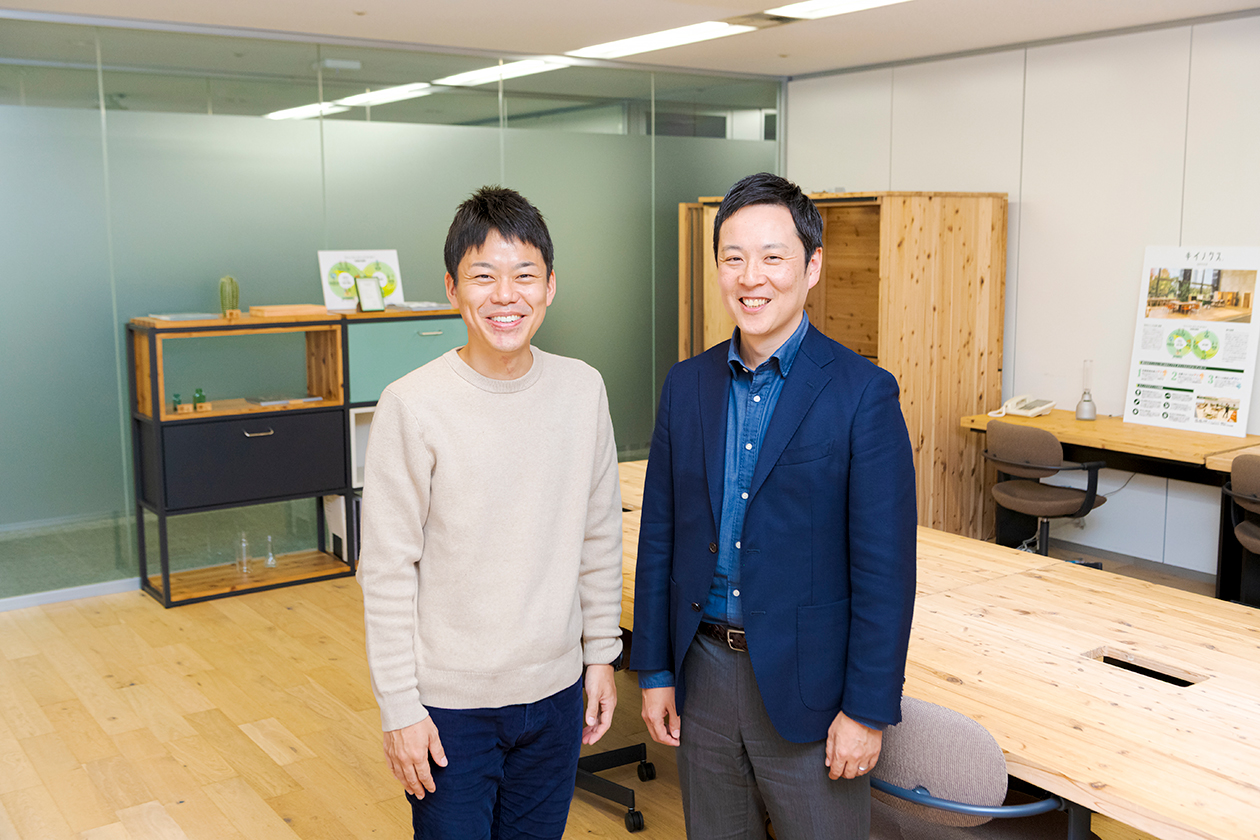
2022年10月から産後パパ育休の制度が始まり、2025年4月から出生後休業支援給付金が開始されるなど、男性の育休取得推進に向けた法整備が進んでいます。BIPROGYでは2024年度よりマテリアリティとして男性育休についてのKPIを掲げ、取得推進に取り組んでいます。今回は、男性の育休取得が組織にもたらす価値について、イクボスと育休取得者が語り合いました。
育休を取得して初めて分かることがある
――おふたりの担当業務などをお聞かせください。
稲葉私は経営企画部の部長を務めています。当部は経営戦略の立案と実行、モニタリングなどをメインミッションとしています。私には高校3年生と1年生の子どもがいますが、子どもたちが生まれた当時は男性の育休取得が一般的ではなかったので、私自身は取得経験がありません。

部長 稲葉啓輔
田中稲葉さんと同じ経営企画部で、経営方針の社内浸透と営業部門支援を担当しています。現在はテレワークが中心で、出社は週1日程度です。子どもは1歳と3歳の2人おりまして、2人目が生まれた2024年3月から2カ月間育休を取得し、5月の復帰と同時に営業部門から現部署に異動となりました。
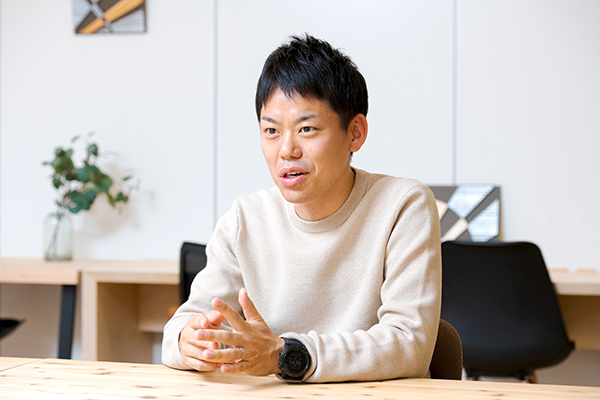
田中裕太郎
――田中さんが育休を取得したきっかけを教えてください。
田中3年前に1人目が生まれたときは、勤続10年で取得できるリフレッシュ休暇を利用して2週間休み、育休は取得せずに育児をしました。2週間だけでしたが、0歳児の育児は夫婦2人でもすごく大変だと気づきました。そのため、2人目の妊娠が分かったとき、上の子も含めた2人の対応を考えると、家事も育児も手が回らなくなると思い、前回よりも長く育休を取らないといけないと思いました。出産予定日の1カ月前に当時所属していた営業部門の上司に育休を取りたい旨を伝えたところ、快諾してくれました。
――育休中はどのように過ごしましたか。
田中1人目のときはコロナ禍だったため、出産の立ち会いも入院中の面会もできず、出産および産後における妻の大変さを実感できませんでした。2人目のときに立ち会えたことで、出産は体への負担が大きく、産後も十分に休めないことを目の当たりにして本当に大変なことなのだと実感しました。
育児は妻が下の子、私が上の子を主に面倒を見ながら、家事は妻が料理、私がそれ以外を担当しました。実際に経験したことで、育児と家事を両方こなすことの大変さがようやく分かりました。子どもと常に接する時間をつくれたことで、育児への理解も深まりました。2カ月という期間はあっという間でしたね。
育休は親の成長機会。広がる視野と高まる生産性
――復帰するタイミングでの新しい部署への異動に不安はなかったですか。
田中復帰の時期がちょうど当社の新たな経営方針(経営方針2024-2026)が動き出すタイミングと重なり、新部署への異動も同時だったので、不安を感じる余裕もないほど慌ただしかったですね。新しい上司となる稲葉さんとは初対面でしたので、どんな方なのかという期待はありました。
稲葉私が経営企画部に異動し、経営企画室を取りまとめる立場になった直後に田中さんが復帰したので、室内の新体制構築の最中でした。チーム全体で助け合える環境があったことが、スムーズな受け入れにつながったと思います。
――育休でメンバーが増減することは、上司からすると大変ではないのでしょうか。
稲葉確かに短期的には戦力減となりますが、長期的に見ると明らかなメリットがあります。育休取得者は、仕事以外の社会的なかかわりが増えるためか、視野が広がり、他者への共感力が高まる人が多いと感じます。さらに、育児との両立のために時間管理が徹底され、生産性も向上します。組織全体にとってプラスの変化をもたらしてくれると実感しています。
田中育休中に見える世界が広がったと感じています。産後の行政手続きの大変さや地域の子育て支援団体のありがたさは強く実感しました。子育てを通じて今まで見えていなかった部分が見えたことは、今後に生きてくると思います。
働き方も大きく変わりました。以前は仕事を残業して対応することもありましたが、2人目が生まれてからは子どものスケジュールを優先し、業務時間内に仕事を終える進め方を意識するようになりました。
――育休取得と評価・昇進についての不安はありましたか。
田中1人目のときは、マネージャー昇進への影響を懸念して育休取得を躊躇しました。特に20代の若手社員は、「キャリア形成の途中で育休を取得してよいのか」という不安を感じるかもしれません。
稲葉当社の人事制度では、育休取得を理由とした評価の不利益は明確に禁止されています。上司として、復帰後の業務成果を公平に評価することを心がけています。
育休は決してブランクではありません。育休中に自己研さんに励む社員もいますし、育児経験を通じて柔軟な思考や新たな視点を得る人も多くいます。

育休から始まる組織改革。多様性を生かすリーダーシップへ
――BIPROGY社内における男性育休に関する変化をどのように感じていますか。
稲葉私の世代にもパパ育休という選択肢があれば、取得していたと思います。現在は経営企画部のような内勤部署だけでなく、営業部門などでも男性の育休取得が当然の文化として定着しつつあります。
最初に育休取得に挑戦した社員や、それを支えた上司、チームメンバーの尽力があって、今があるのだと思いますが、「パパ育休が当たり前」の環境はとても良いことだと思います。当社のマテリアリティにも男性育休について明記されるなど、特にここ2~3年で大きな変化を感じています。
上司として心がけていることは、「育休取得は当たり前のことだよ」という雰囲気づくりです。多くの社員は周囲への負担を懸念して遠慮がちですが、1人の不在で機能しない組織こそが問題です。その調整が上司の重要な役割だと考えています。
田中育休経験者として、後輩たちには「育休は取った方がいい。何も問題ないよ」というメッセージを伝えていきたいですね。身近に経験者がいることで不安も薄らぎ、取得のハードルも下がると思います。そうやって育休取得経験者を増やしていきたいです。
稲葉育休取得者のキャリアアップも重要な指標です。田中さんのような若手社員がマネージャーに昇進していくことで、制度の実効性が証明されます。数年後には、組織長の大半が育休経験者という組織になっているはずです。そうでなければ是正が必要でしょう。
育児に限らず、介護や病気の治療など、さまざまな制約の中で働く社員がいます。そういった人財が働きづらくて離職してしまう環境では、組織の持続的な成長は望めません。多様なバックグラウンドを持つ社員が活躍できる組織づくり、それこそがリーダーの役割だと考えています。
――これから子どもを持つ社員へのアドバイスをお願いします。
田中育休取得を強くお勧めします。産後育児の大変さを夫婦で一緒に体験することで、妻への感謝が深まりましたし、子育てを通じて社会のことに気づく機会も多くありました。効率的に働かざるを得ないため仕事への考え方や進め方も変わり、結果的に家族との時間を増やせたことで絆も強まりました。育休中に子どもの成長だけに寄り添えた時間は、かけがえのない財産です。
稲葉育休をキャリアのブランクではなく、成長の機会として捉えてほしいですね。組織内だけの経験では、時として成長が停滞することもあります。そういうときは、社外での学びを増やすように意識しています。そういった意味で、育休は新たな視点や価値観を得られる貴重な機会だと考えています。