
大阪・関西万博がついに開幕。「2050年の自分」と出会う未来のヘルスケア革命
「大阪ヘルスケアパビリオン」で育まれる思いと技術を次世代につなぐ
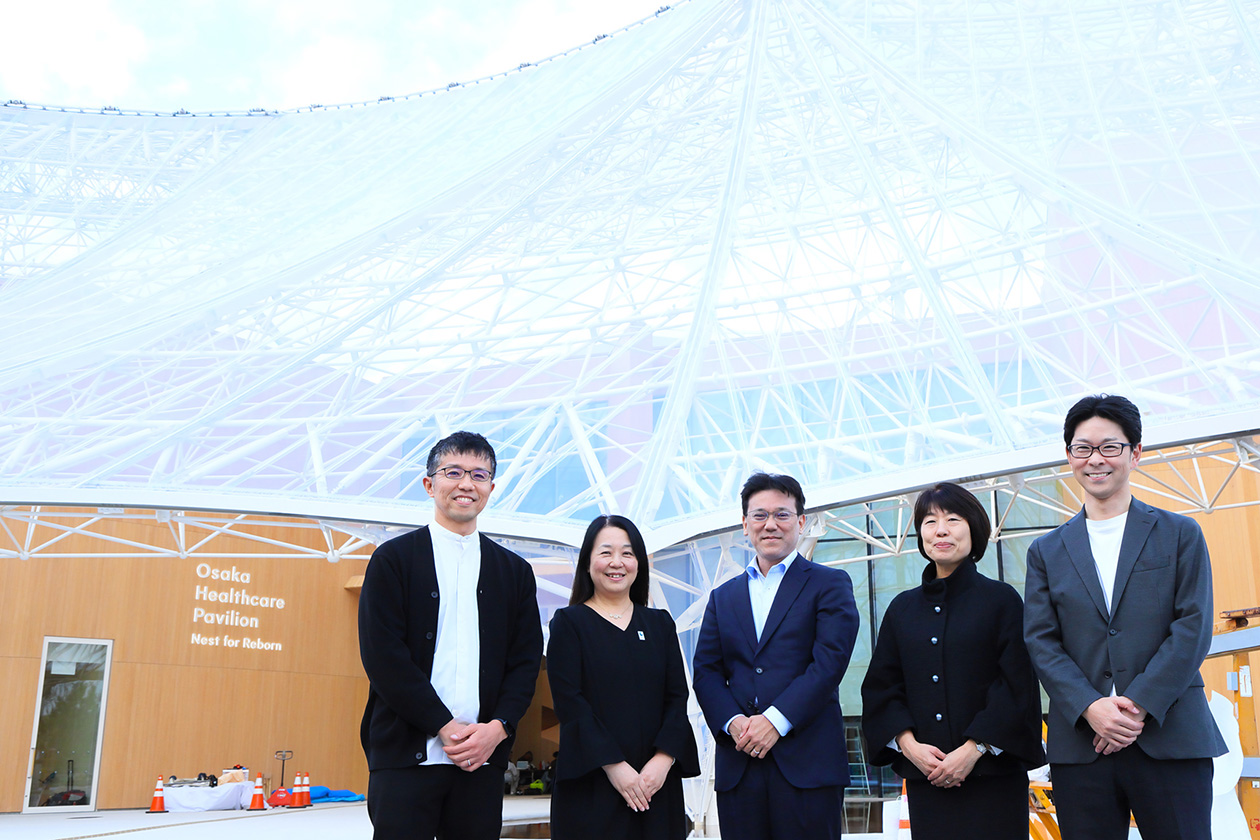
2025年4月に開幕が迫る「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」。テーマは、「いのち輝く未来社会のデザイン」。ポストコロナ時代の新しい社会像に向けて、健康への関心が益々高まる中、注目を集めるのが大阪府・市の「大阪ヘルスケアパビリオン」だ。パビリオンには多くの知恵とアイデアが結集され、「いのち」と「健康」の観点から、健康・医療に関する先進的な取り組みや近未来の暮らしを体験できる展示が行われる。今回、大阪ヘルスケアパビリオン出展総括課長の山縣敦子氏をゲストに迎え、JR西日本の武田善憲氏、博報堂の岩宮克臣氏、PHROの浦田千昌氏、BIPROGYの三宅裕昭が会期中・会期後の取り組みを踏まえた未来のヘルスケア体験の姿を語った(写真:「大阪ヘルスケアパビリオン」前にて/2024年11月末撮影)。
大阪ヘルスケアパビリオンで未知の体験を
――まずは大阪ヘルスケアパビリオンの概要についてご紹介ください。
山縣「大阪ヘルスケアパビリオン」は、「いのち」と「健康」の観点から、健康・医療に関する先進的な取り組みを紹介し、2050年の未来社会を体験していただく場です。まずは自分の身体を知り、意識を変革することで、“生まれ変わる”きっかけになることを願い、テーマに「REBORN(リボーン)」を掲げています。

出展総括課長 山縣敦子氏
――大阪ヘルスケアパビリオンでは、どのような体験ができるのでしょうか。
山縣メインとなる「リボーン体験ルート」では、「ミライのヘルスケア」を体験していただき、未来の自分に出会うことができます。来館者はまず「カラダ測定ポッド」と呼ばれるブースに入ります。そこで、写真やセンサーを用いて髪や脳、心血管など、身体に関する情報を測定します。
次に「ミライのライド」に乗車し、測定した情報を基に作成された「25年後のじぶん(アバター)」に会いに行きます。「シニア世代になった自分は見たくない」という声もありますが(笑)、未来の自分に出会うことは、25年後にどんな自分でありたいかを考えるきっかけになります。
また、「リボーンチャレンジ」エリアでは、新たな技術開発に取り組む大阪の中小企業やスタートアップ441社が週替わりで展示を行います。その他にも、アトリウムでは「ミライの人間洗濯機」や、iPS細胞による自ら動く「心筋シート」などを展示する予定です。また、「ミライのエンターテインメント」を体感できる施設「XD HALL」や大阪・関西の料理人による調理実演やおいしく健康的なフードなどを味わえる「ミライの食と文化」エリアも用意しています。来場者は未来の自分とのバーチャルな対面や、近未来の都市生活体験を通じて、自身の生活や健康について新たな気づきを得ることができます。開催が近づくにつれ、このような未知の体験への期待と関心が高まっていると感じています。



「ミライのヘルスケア」を実現する「カラダ測定ポッド」を開発
――大阪ヘルスケアパビリオンで使われる「カラダ測定ポッド」は、JR西日本が開発されたと伺いました。その経緯をお聞かせください。
武田JR西日本は、博報堂の協力のもと、駅を基点とするヘルスケアマネジメント支援「ステーションヘルスケア」に取り組んでいます。その一環として、パビリオン内に設置される「カラダ測定ポッド」を大阪ヘルスケアパビリオンのご関係者さまと連携して開発しました。これは、個人の健康状態を測定・可視化し、記録する装置です。

ソリューション営業企画部 WEST LABO事業共創
課長 武田善憲氏
浦田「カラダ測定ポッド」では、心血管・筋骨格・肌・髪・脳・視覚・歯の計7つの項目を測定できると聞いています。このように7つの項目を1か所で同時に、しかも約5分という短時間で測定できる装置はないと思います。

代表理事 浦田千昌氏
武田浦田さんのおっしゃる通り、「カラダ測定ポッド」はこれまでにないもので、開発は簡単ではありませんでした。複数の項目を測定するため、各測定機器が干渉しないように設計し、さらに大人から子どもまでどんな体型の方でも測定できるようにする必要がありました。試行錯誤の末、2023年に試験機が完成し、その後も検証を重ねて本番機の製造にこぎつけました。
――大阪ヘルスケアパビリオン内のデータ連携には、BIPROGYのパーソナルデータ連携基盤「Dot to Dot」が使われています。どのように活用されているのでしょうか?
三宅「Dot to Dot」は、もともと企業間のデータ連携をサポートするデータ流通プラットフォームで、パビリオン内の各エリア間のデータ連携・活用にも使用されています。例えば、来館者が「カラダ測定ポッド」で測定すると、データが連携され、測定データを基に体の状態をランク付けしたフィードバックが得られます。

事業開発本部 事業推進三部長 三宅裕昭
また、パビリオン内の「ミライのヘルスケア」エリアでは、食品、ヘルスケア機器、製薬などさまざまな分野の協賛企業がブースを出展します。来館者は、「カラダ測定ポッド」で得られた測定データに基づいて個別化されたサービスを受けることができます。これらは「Dot to Dot」によるデータ連携で実現しています。
大阪ヘルスケアパビリオンにおける「Dot to Dot」の活用イメージ

セルフマネジメントによるヘルスケアをレガシーとして残したい
――万博後も未来に継承したい「レガシー」として、どのような取り組みを推進していきますか。
武田これまで駅は通過点でしたが、今後は多くの人が集まる利点を生かし、皆さんの生活を支える場所にしていきたいと考えています。そこで、万博開催を機に、「カラダ測定ポッド」の技術を活用した新しい取り組み「ステーションヘルスケア」を始動します。
データをアプリで見返しながら、通勤やお出かけのついでに測定を繰り返すことで、些細な体の変化にも気づきやすくなります。また、2025年3月には大阪駅の中央コンコースに「DotHealth Osaka」をオープンさせ、万博の会期中はその中で「カラダ測定ポッドStation版」による測定を体験できるようにします。これらの取り組みが、多くの方々にパビリオンを訪れていただくきっかけになることを期待しています。
万博のレガシーとして、私たちは「ステーションヘルスケア」を通じた新しい健康づくりの文化を根付かせたいと考えています。駅を単なる通過点ではなく、誰もが気軽に健康管理できる場所として発展させることで、次世代に向けた持続可能な社会インフラを築いていきます。

岩宮少子高齢化が進む今、健康管理の重要度は増しています。「カラダ測定ポッド」で測定するだけではなく、継続的な実践が大切です。「継続性につながる要素は何か?」を思案し、たどりついた答えは「セルフマネジメント」でした。日常生活の中で好きなタイミングで計測し、健康状態の変化を把握できれば、それが面白みとなって継続性につながると考えたのです。

マーケットデザインビジネス推進局 ビジネス開発部
チーフビジネスデザイナー/DXコンサルタント 岩宮克臣氏
先ほど武田さんの話にもありましたが、「カラダ測定ポッド」で気になる数値があればそのまま駅ナカでオンライン診療を受け、処方薬はロッカーで待ち時間なく受け取れるなど、駅を基点にさまざまなサービスを展開したいと考えています。広範囲のデータ連携が必要になりますので、BIPROGYの力を借りながら、生活者が安心して使いやすいサービスを目指しています。
三宅BIPROGYとしては約5年前からデジタルを活用した生活者の健康管理を支援しています。その中で、地域住民を巻き込んだ取り組みも行ってきましたが、活動の継続性が課題でした。健康管理の第一段階として、日常の中で「健康状態を知る」機会を持たなければ、生活者にとって有益な情報にたどり着くことができず、健康管理を継続することが難しいのです。しかし、「カラダ測定ポッド」が駅に常設されれば、私たちが感じていた第一段階の課題が解消されます。JR西日本、博報堂、PHRO、BIPROGYの目指す世界観が一致し、大阪ヘルスケアパビリオンの取り組みに関われたことは、大きな前進だと感じます。
――PHROはレガシーにどのように関わっていきますか。
浦田「カラダ測定ポッド」で測定した自分のデータで気になる数値があったら、「これはどうすれば良いんだろう?」と疑問を抱かれると思います。病院に行くほどではないものの、自分で改善を試みたいという方々に、次のアクションを提案するのが私たちの役割です。
具体的には、不足する栄養素や食事、日常生活で取り入れやすいトレーニングなどのアドバイスを行います。私たちは街頭で骨密度や握力の測定を行いますが、参加者同士で結果を見せ合いながらすごく盛り上がるんです。そして、その場で「骨密度を上げるにはどうしたらいいの?」と必ず聞かれ、アドバイスを行うと皆さん真剣に聞き入ってくれます。
計測が最終目的ではなく、「計測して知りたい」との欲求を高め、生活者が興味のある状態でお話しすることが行動変容につながるのだと思います。万博で「ミライのヘルスケア」を体験して終わりではなく、健康管理を継続することが健康寿命の延伸につながるはずです。
大阪・関西万博をヘルスケア文化の起点に!
――2025年4月に開幕を迎える大阪・関西万博、そして未来社会のヘルスケアに懸ける期待をお聞かせください。
武田ヘルスケアが日常に根付くことで、社会課題の解決にもつながります。例えば、忙しくてケアができず、生活習慣病やメンタルヘルスの問題に至った人を減らすことができれば、人手不足に悩む企業や地域医療にとっても大きなメリットです。主要な駅だけでなく、ヘルスケアの支援が不足している地域でもITやネットワークの力を活用して新たな支援を提供していきたいと考えています。
岩宮ジムでの運動、服薬、健康食品の購入など、日常のさまざまな行動に関わる企業が「カラダ測定ポッド」で測定したデータを取得し、生活者のヘルスケアを支援していく――。生活者はこうした支援を受けることで、自身の健康を楽しみながら管理できるでしょう。万博の開催は、こうしたセルフマネジメントを実現するために動き出す絶好のタイミングだと思っています。
浦田「カラダ測定ポッド」で測定したデータに加え、運動や服薬といった日常の行動がデータ連携されていつでも把握可能な状態であれば、病院受診の際も「今の自分」に適した治療を医師に判断してもらいやすくなります。治療方法はもちろん、食べ物や運動など、その人に合うものは千差万別。データを基に自分と相性の良いものを選んだり、見つけたりすることが楽しくなれば、生活者の健康への興味もより高まるのではないでしょうか。
三宅今、改めて再認識しているのが、万博は「文化」を発信する場だということです。2050年の未来社会に向けて、セルフマネジメントにより病気を予防することが当たり前となる文化を創る必要があると考えています。2050年には、生活者が駅で普通に自分の健康管理をする時代になり、「これはいつから始まったんだろう?」と疑問に思いネットで検索したら、「ヘルスケアの新たな文化は2025年大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオンから始まった」と分かる。そんな未来の実現を願っています。
山縣大阪ヘルスケアパビリオンは、展示を含めると450社を超える企業の最新技術とアイデアが詰まった唯一無二の存在です。圧倒される展示内容によって未来社会を体験できますので、会期中は一人でも多くの方に足を運んでいただきたいです。また、大阪府・市としても、パビリオンでの取り組みを皆さんとともに、レガシーとして残していきたいと考えています。特に、手軽に健康情報を把握でき、パーソナライズされたサービスを提供できる「リボーン体験」が社会実装されれば、健康寿命と平均寿命の差を縮める大きな一歩になると考えています。
大阪ヘルスケアパビリオンでは、「いのち」や「健康」をテーマに、子どもから大人まで楽しみながら未来の可能性を感じられるさまざまな体験を提供します。これらの体験を通じて多くの方々が健康への意識を高め、その小さな変化が大阪から日本へ、そして世界へと広がることで、より健康的で持続可能な社会の実現につながっていく──。「REBORN」という名称には、そのような未来への願いと可能性が込められているのです。



