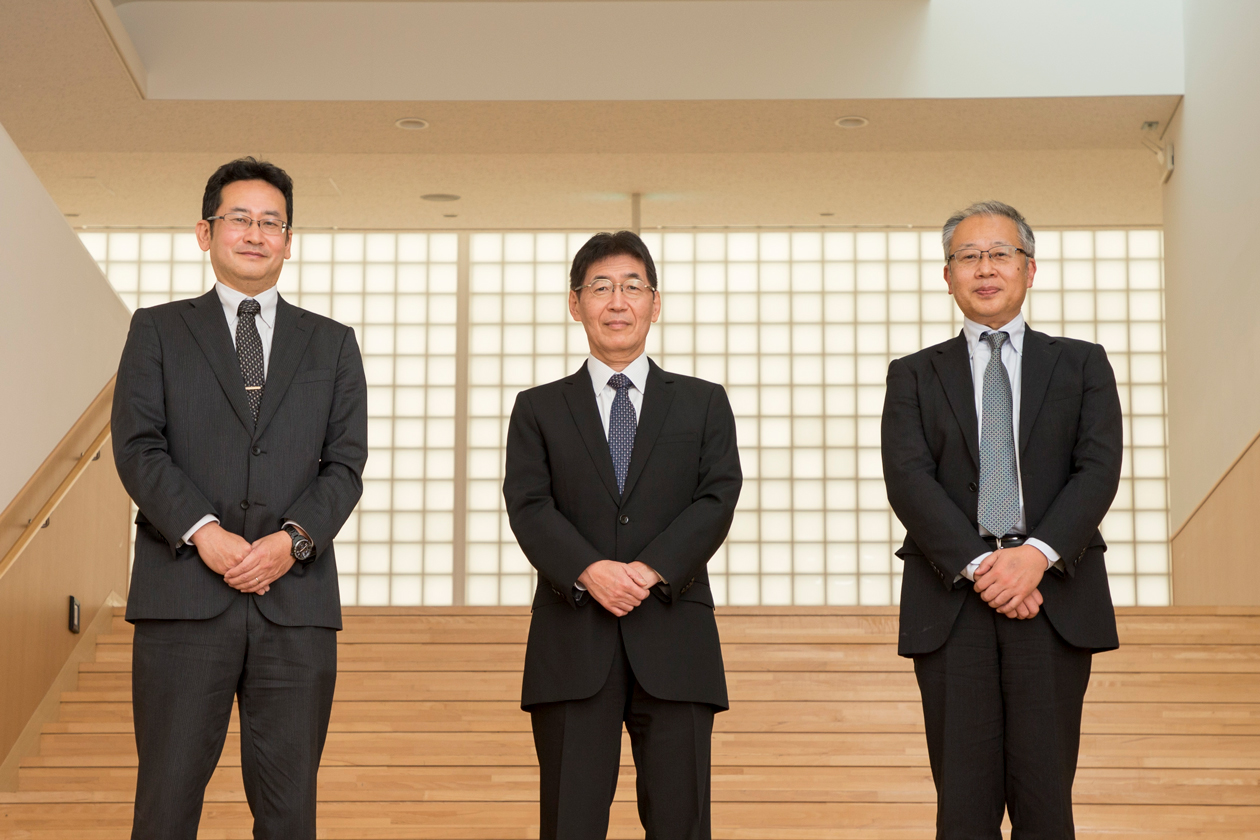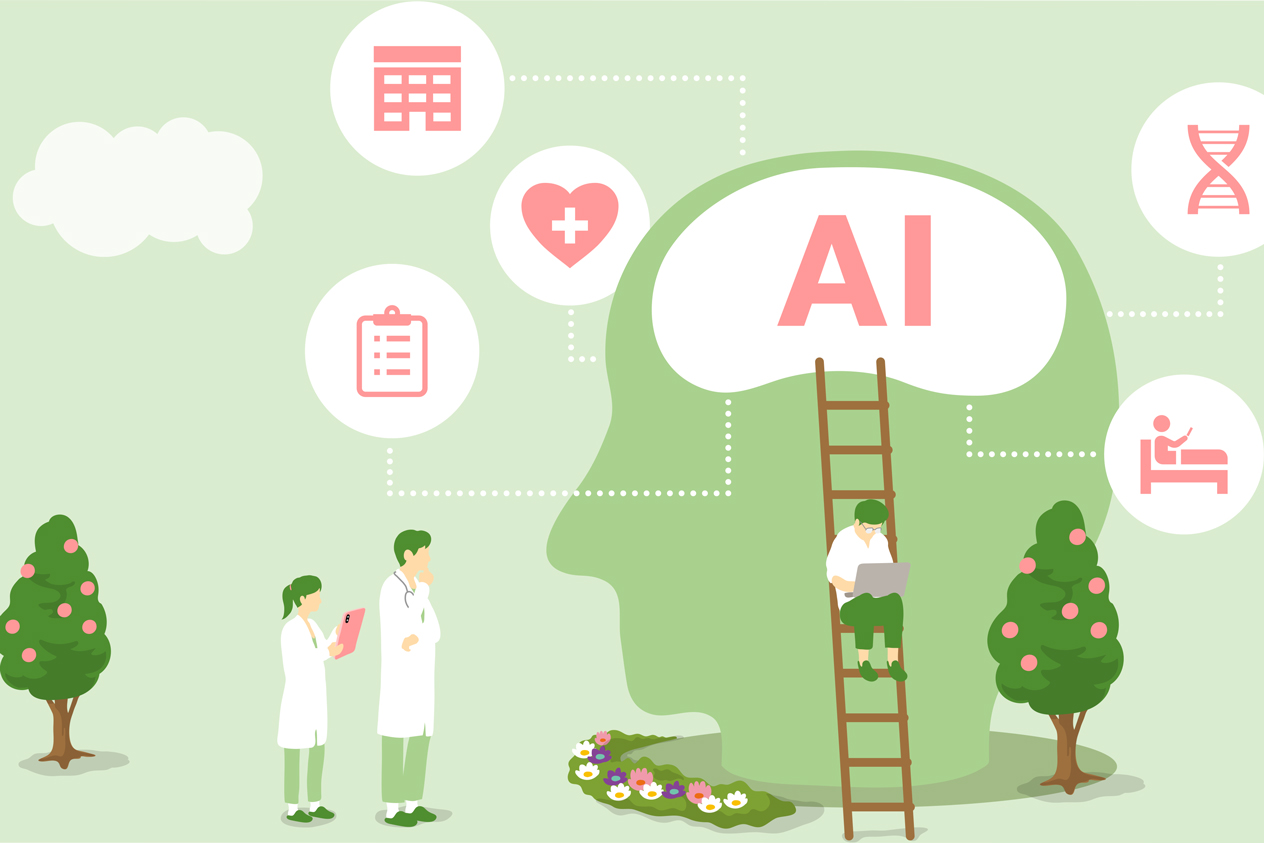「Muse細胞」発見者が見つめる医療イノベーションの未来
成功と失敗を越えた視点がもたらしたもの

2023年6月8日と9日の両日にわたり開催された「BIPROGY FORUM 2023」。その初日の特別講演では、「Muse細胞のもたらす医療イノベーション」と題して東北大学大学院医学系研究科 教授の出澤真理氏が登壇。多能性幹細胞「Muse細胞」は、2010年に出澤氏によって発見されたもので、血液によって身体の傷ついた部分に運ばれ、それを修復する能力を持つことから、身体の恒常性の維持という重要な役割を担っている。2018年以降、心筋梗塞などの分野で治験が進められており、安全性と有効性が確認されている。今後、大きな期待を寄せられるMuse細胞。出澤氏が語ったその可能性と未来、そして研究プロセスや発見の経緯の中にはビジネスやイノベーションにも通じる発想のヒントがあった。
社会から期待を集める「Muse細胞」
私たちの身体は、常に有害な要素にさらされている。その中には、紫外線のような外側からの攻撃もあれば、ストレスのように内側で生まれる要素もある。また、健康を著しく害するほどではなくても、食物の一部に有害物質が含まれていることもある。このような事情から、身体は日々ダメージを受けている。しかし、私たちがおよそ80~90年の人生の中で身体の恒常性を維持できるのは、身体がそれらのダメージを修復する機能を持っているからだ。一体何がそのような機能を可能にしているのか――。
東北大学大学院医学系研究科の出澤真理教授らが2010年にその発見を発表した多能性幹細胞「Muse細胞」は、身体の修復という重要な役割を担っている。出澤氏はこうした役割を「身体の総合メンテナンス会社」と例える。

教授 出澤真理氏
「ビルを長期間機能させるためには、電気やガス、建具などを日々管理する必要があります。それがメンテナンス会社の仕事。Muse細胞は同じような役割を担います。しかも、『総合』がついています。『ウチは電気だけ』とか『ガスだけやります』というのではなく、Muse細胞は血液を通じてあらゆる臓器に配給され、傷ついた細胞を修復しているのです」
Muse細胞はES細胞(胚性幹細胞)、iPS細胞(人工多能性幹細胞)に続く「第3の多能性幹細胞」と呼ばれることもある。Muse細胞は日々少しずつ傷ついている臓器に血液を通じて供給され、傷ついたり死んだりして機能を果たせなくなった細胞と同じものに分化することで健常な細胞に置き換えているという。身体には多様な臓器、多様な細胞がある。なぜ、Muse細胞は都合よく特定の細胞に分化することができるのだろうか。
「Muse細胞は壊れた細胞を食べて、その味を感知し、食べた細胞と同じ細胞に分化します。こうして、身体の恒常性が維持されているのです」と出澤氏は説明する。例えば、心筋細胞が壊れれば、そのことを示す警報物質が放出される。そのシグナルを感知したMuse細胞が該当部分に集積して、壊れた細胞を食べ心筋に姿を変える。肝臓の細胞が死んだら同様に、Muse細胞がそれを食べて肝臓の細胞に分化する。
「Muse細胞の能力を活用することで、多様な疾患に対する治療が可能になると考えています」と語る。現在、Muse細胞を活用する形で心筋梗塞や脳梗塞などさまざまな疾患を対象に治験が行われているという。
臨床現場での手応えも。Muse細胞が拓く医療の新たな地平
Muse細胞を用いた治験は2018年にスタートした。治験では、基本的にドナーのMuse細胞が用いられる。患者本人から採取することも可能だが、細胞を増やすのにかかる時間などを考えると、ドナー由来のMuse細胞を投与するのが合理的だという。
「Muse細胞の大元は骨髄の中にあると考えられています。そこから少しずつ、血液中に供給される。血液に含まれるMuse細胞の量は個人差や健康状態などによる差があり、変動もしますが、リンパ球などの中の千分の1~数千分の1程度の割合です。臓器移植ではHLA(ヒト白血球型)適合検査が行われ、適合しなければ移植はできません。免疫拒絶が起きるからです。一方、Muse細胞の場合、例えばAさんからもらったものをBさんに直接点滴することができる。免疫抑制剤も不要です」
臓器移植の場合、血縁者から移植を受けるケースが多い。血縁者はHLA適合の確率が高いからだ。血縁者以外のドナーを探そうとすると、適合率は数万人に1人ともいわれ、患者は長い期間を待たなければいけない。また、移植後には長期にわたって免疫抑制剤を投与する必要もある。こうした要件を必要としないという特徴をMuse細胞は備えているという。
そして、投与方法は点滴と、非常にシンプルだ。出澤氏は多様な投与方法の検証を経て、点滴が最も有効だと説明する。
「当初、血流が豊富でない組織では、局所投与のほうが効果的ではないかとも考えました。しかし、実際に検証してみると脊髄のような血流の比較的少ない組織でも、点滴で投与したほうが、Muse細胞がきちんと届いている。警報シグナルをキャッチして、傷ついた場所に正確に集積し臓器を修復しているのです」

治験が始まって5年ほどになる。その最初期にMuse細胞の投与を受けた患者に、今も免疫拒絶の兆候はないという。さまざまな医療機関が実施している治験は順次結果が出されているようだ。
例えば、東北大学脳神経外科グループが中心に行った脳梗塞治験である。Muse細胞製剤と偽薬を用いた二重盲検(編注:評価時のバイアスを排除するため、患者と医師ともにどちらが投与されたか分からない状態)において行われた治験のケースだ。対象は寝たきり、失禁か、歩行やトイレなどに介助を必要とするような身体機能障害を持つ患者で発症後2〜4週で1回のみ点滴投与。1年後、Muse細胞を投与された患者の約7割が、介助なしにバスや電車に乗れる状態にまで回復し、約3割が職場復帰できる状態になった。一方、偽薬を投与されたグループは、職場復帰レベルにまで回復した患者はゼロであった。
“失敗”がきっかけで開いたMuse細胞への扉
時間を遡って、Muse細胞発見までの研究をたどってみよう。「失敗には成功のタネが隠れています。成功の多くは、失敗を装って近づいてくる」と出澤氏は話す。
20年ほど前、出澤氏は骨髄の間葉系幹細胞を研究していた。あるとき、研究室の技術補佐員が「培養していたら気持ち悪い塊ができているので捨てていいですか」と聞いてきたという。
「よく見ると毛のような構造があり、色素細胞らしきものも混じっていました。多能性幹細胞のES細胞に似ていると思い、詳しく調べてみると、そこには身体を構成する三胚葉性の細胞が存在していました」。ES細胞に似ていたが、この細胞塊はES細胞のような無限増殖は見せなかった。そこで、出澤氏は骨髄間葉系幹細胞の中に多能性を持つが腫瘍性はない有用な細胞があるかもしれないと考え、所属していたグループを挙げてその正体を突き止めようとした。
「正月返上で実験をしたときもありますが、何年も空振り続きでした。諦めかけていたある日、飲み会に行ったことがきっかけで扉が開きました」
急な誘いでもあったため、実験を早めに切り上げて飲み会に駆けつけた出澤氏。その翌日、研究室に戻ると実験途中の細胞が死に絶えていた(ように見えた)という。「前日に急いで実験を閉じたためか、培地を入れたつもりが間違えて消化酵素を入れてしまったらしいのです。ショックのため、何が起きたのか、一瞬分かりませんでした」と振り返る。しかし、「失敗した」からといってそれをすぐに捨てたりはしなかった。
「失敗したときは、それをよく見て、遊んで、それから捨てるのが私のクセ。それを調べてみると、生き残っている細胞が少しありました。それを集めて培養したところ、多能性幹細胞だと分かった。これを『Muse細胞』と名付けたのは、共同研究者の藤吉(好則)先生(京都大学大学院理学研究科教授・当時)です」
2010年に発表されたMuse細胞は、メディアにも多く取り上げられ話題になった。その8年後に治験が始まり、今後のさらなる活用に向けた成果が待ち望まれている。
「自然科学では成功も失敗もない、というのが私の信条。人間が一方的に『こうあってほしい』とか『こうであるはずだ』と考えて、その期待値を超える結果が出れば『成功』、そのラインに届かなければ『失敗』と呼んでいるにすぎません。すべては、等しく自然現象です。成功とか失敗といった言葉に心をとらわれず、バイアスを排除し、ありのままに現象を見ることが発見のきっかけを作るのです」
そのように世界を見るクセが、Muse細胞の発見につながった。出澤氏はこう続ける。
「失敗というのは、単に仮説通りにいかなかったということ。そこで、ちょっと待てよと立ち止まって、『もしかしたら、ここから何かが生まれるかもしれない』とポジティブに考えるクセをつければ、きっと何か新しいことを発見できると思います」
この世界には確かに人智を超えたことがある。どこかに埋もれたまま、新たに発見されることを待っている事実や現象、叡智は限りない。ビジネスの世界でも、新しいアイデアやビジネスモデルの芽、人々の幸福へとつながる画期的なテクノロジーのヒントも誰かに発見されることを待っているに違いない。そこには、Muse細胞を活用した明日の医療イノベーションも含まれるだろう。