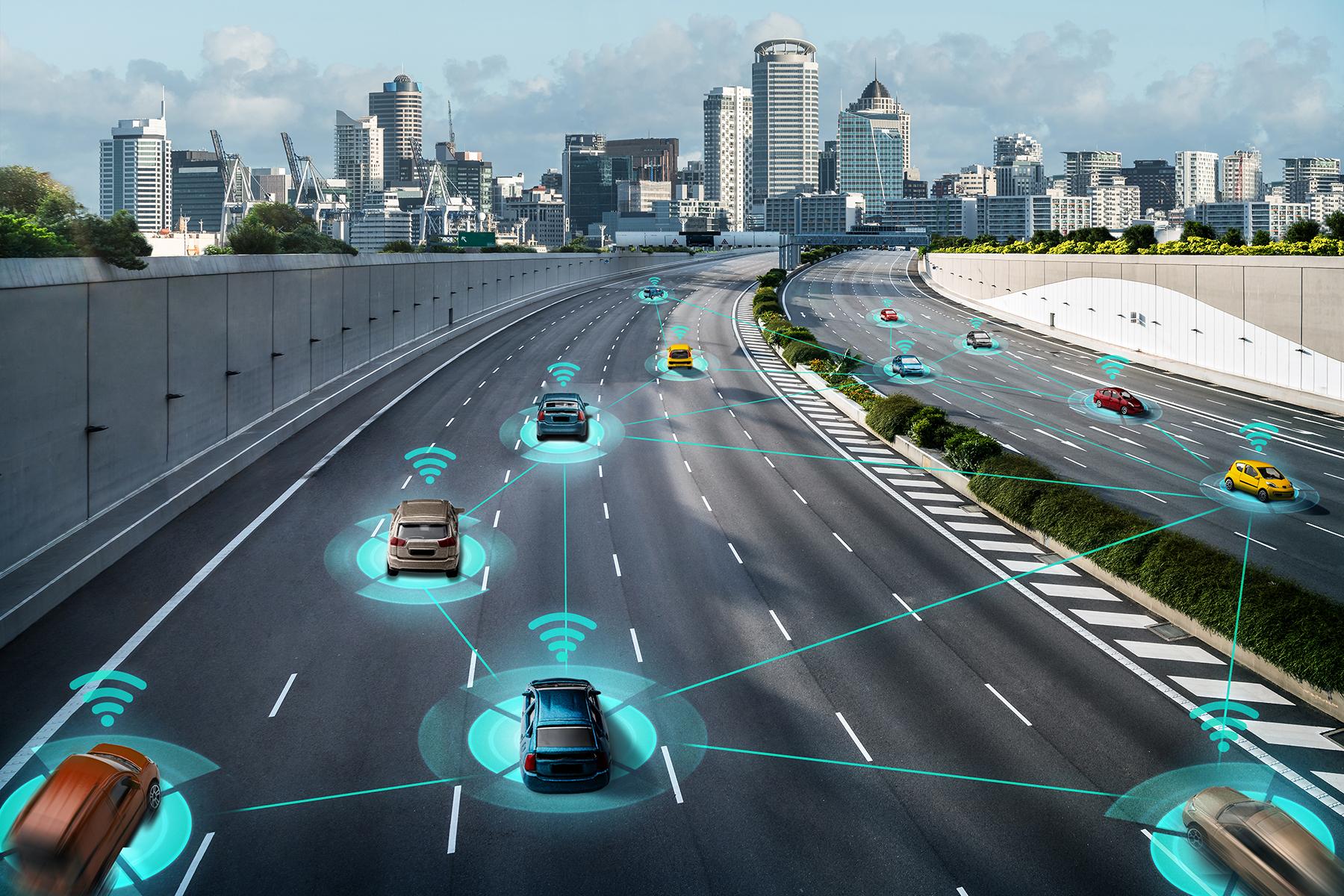コロナ禍を超えて 「青春」を生きる
建築家・安藤忠雄氏が示唆するサステナブル社会の方向性――BITS2020関西開催(2)

世界的な新型コロナ禍は、高度化したグローバル経済の脆弱性はもとより、際限のない経済成長を是とする資本主義社会の限界を浮き彫りにした。同時に大気汚染改善なども各地で報告され、図らずも私たちは、今般のコロナ禍を通じて経済活動が環境に与える各種の影響や「地球は1つの共同体である」という事実に改めて気づかされたと言える。本稿では、世界的な建築家である安藤忠雄氏が日本ユニシス主催のオンラインセミナー「BITS2020関西」(2020年12月7日開催)で語ったメッセージに心を傾け、私たちが今後どのように地球環境と共存し、持続可能な社会の実現に向けて行動していくべきかを考えたい。
「青いりんご(未熟)」のまま人生や社会の可能性を追い続けたい

安藤忠雄 氏
今、日本は「人生100年」と表現されるかつてない時代を迎えている。しかし、その中を生きる私たちは、長い時代を生きるにあたり、生きるための基盤となる持続的な環境をつくっていけるのか――。
兵庫県立美術館の屋外スペースには、高さ2.5メートルほどの「青いりんご」のオブジェがある。これは同館を設計した世界的建築家・安藤忠雄氏が近代米国の詩人サミュエル・ウルマンの「青春の詩」から着想を得てデザインしたもの。その背景に触れながら、BITS関西の基調講演に登壇した安藤氏はこう語る。
「青いリンゴには、『いつまでも熟し切ることなく、明日への希望に満ちた気持ちを大切にしてほしい』という思いを込めています。好奇心を胸に抱き、自由な発想と勇気を持って行動することで社会は変わっていきます。大きく時代が変わろうとしている今、人生でもビジネスでも、必要なのはそんな『青いリンゴ』の精神ではないでしょうか。持続可能な環境というテーマについても、日本には独自の自然に依る感性があるのですから、それを『青いリンゴ』のチャレンジ精神をもって、次なる時代の価値観として世界に発信していったらいいのです」
持続可能な未来を切り拓く、カギは「自然」だという。例えば、春。大阪市中心部の中之島の川沿いを歩いていると満開の桜が幾重にも重なりあった光景に包まれる。息をのむほどに美しい、生命の季節。冬もまた素晴らしい。雪の積もった京都・銀閣寺の姿を想像してほしい。「この風景の感動が、心を湧き立たせ、次へと向かう創造心を喚起するのです」と安藤氏は笑顔を見せる。
一方で、その世界に誇るべき、四季を愛でる日本人の感性が、現代は失われつつあると、警鐘を鳴らす。確かに、1970年頃以降、日本は世界有数の経済大国へと成長し、目の前の豊かさに安心しきってしまったように見える。同時に傲慢になり、自然破壊は進んだ。1990年代以降はバブル崩壊やリーマンショックなどの経済社会の大きな変化、さらには多くの自然災害なども重なっていく。自然と共生する自然観は、日本文化の原動力だ。未来が不透明な今、日本人がやるべきことは、近視眼的な利益の追求ではない、自分たちの足元を今一度見つめなおすことではないか。
そして安藤氏は、自身の原点の1つとなっている若き日の10カ月間の世界旅行に触れながらこう続けた。
「ロシアを経由してヨーロッパ諸国、そしてアフリカ大陸。その後インドを経由して帰国の途に就きました。その中で感じたのは、『それぞれの国にそれぞれの自然、生き物がいて、人々の生活がある』ということ。地球規模で環境が激変する現在、私たちは『地球の中で生きている』ことを意識しなければなりません。必要なのは、『木を切ったならば、次の世代に続く苗木を植える』感覚、共生の思想なのです」
多くの日本人がなくしてしまった「自然を再生させる」という責任感と勇気
安藤氏は、瀬戸内海に浮かぶ小さな島の再生プロジェクトに30年以上携わっている。この「直島(なおしま)」は、島内の至る所に自然と現代アートの融合があふれる「文化の島」として広く知られ、現代アートの美術館を軸としながら、一方で築100年の古民家に造られた「ANDO MUSEUM」や既存の古い建物にアートを融合させる「家プロジェクト」などが展開されている。
プロジェクトは、ベネッセホールディングスの福武總一郎氏の発案によって1988年にスタート。安藤氏は1987年に福武氏に招かれ「この島を美術館の島にしたい。世界中の芸術家がここに自分の作品を展示したいと熱望する迫力ある美しい島をつくり、瀬戸内海全域を文化と芸術で覆いつくしたい」という構想を聞かされた。だが、安藤氏は「実現できるだろうか」と不安を覚えたという。
当時の直島は、銅の製錬による煙害ではげ山となっており、自然豊かで風光明媚とは言いにくい状況だった。しかも、岡山市内からのアクセスであればローカル線の電車に乗って約1時間。最寄りの宇野港から船に乗り換えて、さらに20分程度の場所である。『都会的で便利なものが価値あるもの』と捉える時代。その中にあって「この島で美術をやっても誰にも見向きされない」と考えたのは無理からぬことだろう。
しかし、安藤氏の心を動かしたのは福武氏の情熱だった。「“不便でもいい、非合理的でも構わない。ここにしかないものがあれば必ず人は来てくれる”と福武さんは言うんです。最初から無理だと考えていたことを反省しました。自分も含めた多くの日本人が失っていた『自然を再生させる責任感と勇気』を福武さんは持ち続けていたのです」と振り返る。
一連のプロジェクトによって島の自然も再生した。森林の養分が海に注ぎこむようになり、多くの魚介類を育む環境を生み出している。これを支える取り組みの1つが、安藤氏と弁護士の中坊公平氏、心理学者の河合隼雄氏を呼びかけ人に設立されたNPO法人「瀬戸内オリーブ基金」だ。不法投棄されたごみの回収や痩せてしまった土地の回復、植林などを通じ、瀬戸内海エリアの自然環境保全を目的に活動している。
安藤氏はこれらの活動を踏まえつつ、「自然を守ることには持続力が必要です。そのためには、勇敢で自由な感性を持つ未来世代を育てバトンをつないでいかねばならない」と語る。
その一環として設立されたのが「こども本の森 中之島」という図書館だ(大阪府、2020年7月開館)。国内外から寄贈された絵本や児童文学など約1万8000冊超の書籍が収蔵され、館内はもちろん、隣接する中之島公園内の広場や芝生の上で子どもたちは自由に本を読むことができる。周囲の川沿いに桜を植樹する活動も開館以前から継続されており、植樹当初3m余りだった桜の木は今では倍以上に成長している。
明日への希望に満ちた「青いリンゴ」であれ
「こども本の森 中之島」は、安藤氏自身が大阪府知事や大阪市長をはじめ、在阪の企業を中心とした市民の協力をとりつけ、実現した。原動力は「自身を育ててくれた大阪のために、未来を担う子どもたちのために、自分に何ができるか」という安藤氏の思いだった。同館入り口には、その情熱を体現するように冒頭でも紹介した「青いりんご」のオブジェが設置されている。
安藤氏は「不透明さの増すこれからの時代、『覚悟と持続力、そして想像力と勇気を持って世界を変えていく』情熱、生きる力が重要です。そんな力強い精神的土壌の上に、新時代の概念であるデジタルコモンズ、日本人が持つ自然への畏敬の念など、多様な価値観を兼ね備えた次の世代が育っていってほしい」と語り、こう続ける。
「人類は約78億人となり、『地球と共に生きること』が問われています。今、2025年の大阪万博に向けた取り組みにも参画しています。その中では『地球のために、大阪のために、生きていくことの楽しさのために、自分自身に何かできるか』を大切にしています。起点は、私たち日本人らしい豊かな感性であり、たとえ未熟で酸っぱくとも明日への希望に満ちあふれた青いリンゴの精神です。私は、国際社会の中でそれらを発揮していくことで、日本が世界をリードする存在になっていくのではないかと考えています」
私たちは、地球環境といかにして共生していけばよいのか、そして社会に対して何ができるのか――。今一人ひとりの生き方を改めて考えていく必要がありそうだ。