
過去と現在と未来をむすぶ文脈を紡ぎ、組織の進化をめざすコーポレートブランディングの挑戦。【後篇】
10年以上続くコーポレートブランディングの核心とは?

約10年にわたって連続性を失うことなくコーポレートブランディングを進化させてきたBIPROGY株式会社。その取り組みを「コーポレートブランディング第一期」と「第二期」に分けて紹介してきた本対談の最終章は、現在のコーポレートコミュニケーションに光を当てます。とかく「企業のお知らせ役」になりがちな広報部ですが、広報の本質的な役割は「パブリックリレーションズ」、つまり「社会とのよい関係づくり」にあります。自社の「らしさ」を効果的に伝えるBIPROGY流広報の哲学とは、どんなものでしょうか。
◼︎前篇・中篇はこちら
本記事は株式会社エンビジョンから提供いただき掲載したものです。
https://envision-inc.jp/insights

滝澤素子 様
BIPROGY株式会社 広報部長
1989年に新卒で入社したコンピュータ関連の出版社アスキーで、広報パーソンのキャリアをスタートさせる。そこからいくつかの会社を渡り歩くも一貫して広報の仕事ひと筋。2000年に日本ユニシス株式会社に入社。2019年に広報部の中でもとくにマスコミ対応を担うPR室長に就任。その後、2020年より現職。
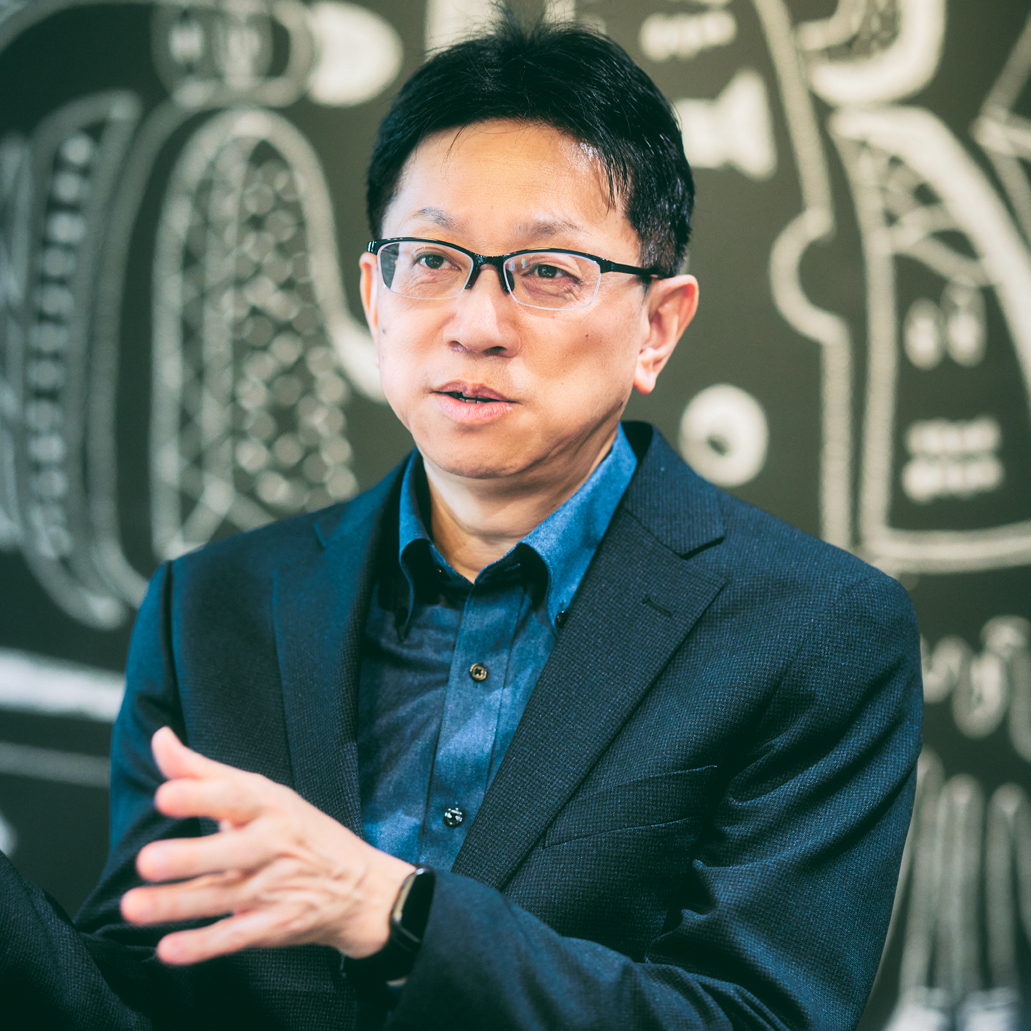
畠中栄 様
BIPROGY株式会社 広報部 BX室長
1993年にSEとして日本ユニシス株式会社に入社。自社プロダクトやサービス開発に関わる中で「人と組織」の探究を指向。2011年にマーケティング部門に異動し、今も使われ続ける‘Foresight in sight’の企業ステートメント策定に参与。その経験を活かし、2015年より広報部でコーポレートブランディングに取り組む。
※BX=ブランドトランスフォーメーション

香山未帆 様
BIPROGY株式会社 広報部 BX室
2021年、実業団チームのバドミントン選手としてBIPROGY株式会社に入社。女子シングルスで数々の大会に出場し、2023年の全日本実業団ではチームの優勝に貢献。 2024年に選手を引退してからは、大学で学んだブランディングを実践したいと自ら希望し、コーポレートブランディングに携わる。

藤巻功
エンビジョンCOO兼CBO
事業成長を加速させ、人を動かす「クリエイティブのチカラ」を信じているブランディングの専門家。国内大手広告代理店等を経て、インターブランドジャパンにて戦略ディレクターとして、グローバルを含む多様な業界の大規模プロジェクトを多数リード。その後、楽天グループ、KPMGコンサルティングを経て、envisionでは、社会課題を解決するWoWなブランド・クリエイティブ開発、ブランディングの民主化に邁進する。
- Contents
「社会とのよい関係づくり」を考える広報へ。
藤巻 みなさんが所属しておられるのは広報部ですが、広報とコーポレートブランディングは車の両輪のようなものですよね。コーポレートブランディングを進める中で、広報の位置付けはどのように変わりましたか?
滝澤氏 まず世の中全体の流れとして、コロナ禍で潮目が変わりましたよね。自社の製品の価格やスペックを訴えるだけでは、もう選ばれる理由になりません。その企業の哲学が問われているのが今で、たとえ企業規模が小さくても、真剣に社会をよくしたいと考えている会社が評価されているのを実感しています。これまでの広報はどうしても費用対効果を広告換算値として測ることにばかり目が行きがちでしたが、そもそも広報が担う本質的な役割は「ステークホルダーとの良い関係づくり」だと考えています。ですから2020年に広報部長になってから、ずっと「私たちは一方的な情報提供屋じゃない」と言い続けてきましたし、求められる仕事の難易度も上がったと思います。

畠中氏 フィリップ・コトラー氏のいう「マーケティング5.0」へ向かう流れとも符号していますね。2.0は合理性が求められた時代で、どれだけ高機能でリーズナブルかで評価されていました。続く3.0の時代に評価されたのは体験価値、4.0になるとそこに「自己実現」が入ってきます。5.0はそれをDX化する時代です。ブランディングや広報も、2.0の時代は目新しい何かを打ち出して露出を高めればよかったけれど、3.0あたりから「そのブランドになぜ価値があるのか」を語る「文脈」が重要になってきました。
滝澤氏 広報って社内外に開かれた窓のようなもので、自社の文脈や「あり方」を語ってステークホルダーとの関係づくりを担う要の部署だと思っています。そういう観点からいくと、大企業かスタートアップか、とか、発注する側かされる側か、という線引きも、あまり意味を成さないんですよね。これからは協力会社とも、同じ志を持つ仲間としてフラットな関係であるべきだと考え、そんな風に社内の認識を拡げているところです。それはメディアのみなさんに対しても同じで、「今、世の中に何を伝えるべきなのか」という着眼点を、一緒に考えていこうという関係性になっています。
藤巻 なるほど。広報の本質的な機能と役割ですね。世界的な広告賞の祭典でもあるカンヌライオンズのPR部門において、ビヘイビアチェンジが重要視されていますよね。PRは世の中に新しい概念や習慣を生み出す仕事です。2010年に初めて提示され、2015年に「バルセロナ原則2.0」、そして2020年に「バルセロナ原則3.0」が提示されましたね。一方で、オウンドメディアの役割も変わってきているんでしょうか?
畠中氏 私たちのオウンドメディアは、もともとお客様向けの広報誌「Club Unisys」で展開していた内容をウェブに落とし込んだものですが、社名変更以降は、世の中を明るく照らしていきたいという思いを込めてBIPROGY TERASUと名付けて、内容も進化しています。中にはビジネスとは直接関係ない、多様性について考えるきっかけを提供する読み物もあって、たとえば誰かの個人的な生きざまを伝える「a storyteller」というシリーズでは、IT業界外の学者さんやアーティストなどにお話を伺っています。また、「Break Through!」というシリーズでは、弊社所属のバドミントン選手が登場しています。

滝澤氏 弊社が主催するリアルイベント「BIPROGY FORUM」においても大切にしていることは同じです。オンライン・リアルの双方で、人間味と多様性というコンセプトを伝えていく姿勢は、より強くなっていますね。
「スポーツで社会にギフトを届ける」、 実業団スポーツと企業ブランディングの関係性。
藤巻 御社のユニークな点としてバドミントンの実業団をお持ちであることが挙げられますが、創部はどういった経緯でしたでしょうか?

https://www.biprogy.com/badminton/
滝澤氏 はい、まず1989年に男子チーム、続いて2007年に女子チームが誕生しています。その背景には、世界に挑めるような実業団を持つことで、社内の求心力を高めたいという思いがありました。創部以来、多くの日本代表選手やメダリストを輩出しており、今はナショナルチームの約30%が弊社所属の選手で、社会的にも認知されるようになったと感じています。
畠中氏 会社のシンボルスポーツという位置付けになっていますが、国内外の大会で活躍することができれば社会への「夢と希望」のギフトにもなり、広報以上の価値があると思っています。
藤巻 香山さんも元選手で、2023年全日本実業団バドミントン選手権大会の決勝戦で優勝を決めるなどチームに貢献してきたとお聞きしましたが。
香山氏 はい、ありがとうございます。2024年にバドミントン選手を引退しましたが、次のキャリアを考えた時、ブランディングに関わりたいと自分から手を上げてBX室所属となりました。大学時代に、授業でブランディングを学んで、人の気持ちを突き動かす可能性に魅力を感じ、興味を持ったのがその理由でした。

香山氏 現在、実業団とブランディングとを接続する試みとして、「見えるバドミントンラジオ」というニュース動画配信を社内向けに行っています。企業風土や社員の気持ちにいい変化が生まれるきっかけになればと思い、草の根的に続けています。
通常は社内向けに配信されている「見えるバドミントンラジオ」のうち、一部はYouTubeで特別公開されている。
畠中氏 選手たちが生み出すドラマは、弊社が大切にしている「人間味と多様性」というキーワードにもつながっていて、他社には真似できない個性になっていると思います。
藤巻 スポーツとコーポレートブランディングの関係性は、引き続き重要なテーマになりそうですね。
集団的意識の進化を起こし、自律型組織としてよりよい未来へ。
藤巻 ではこれからの組織課題について教えていただけますか?
畠中氏 私の捉え方として、企業活動には「生存」と「存在」という2つの領域があると思っています。「生存」とはお金を稼いで企業を存続させることで、そこには当然「しんどいけれどやらなくてはならない仕事」もあります。一方、ブランディングとかパーパスが関わるのは「存在」の領域で、ここでは自社が社会の中でどういう役割を果たし、どんな未来を目指すのかという問いと向き合う必要があります。明日の締切が迫っている中で、10年後の自社の価値を考えている余裕がないのは当然ですが、意識レベルが高くなればなるほど、この2つの領域が相互的な関係であることが理解できると思うんです。そこまで社内みんなの認識を上げていくのも、自分たちの役割です。

滝澤氏
書籍「ティール組織」に出てくる組織モデルと照らし合わせた時に、自分たちの「集団の意識」がどのレベルまで進化しているのか、現状を把握し理解することが大事ですね。
(注:著者のフレデリック・ラルー氏は、組織モデルをその進化過程ごとに色分けし、レッド/衝動型、アンバー/順応型、オレンジ/達成型、グリーン/多元型、ティール/進化型の5分類で説明している)
この書籍に出会ったのは2018年でしたが、読んでものすごく感動して、当時専務だった平岡(同社前社長)に長文メールを書いて夜中に送ったぐらい(笑)。正直なところ当時の私は、マーケティング的にコントロールするという広報の仕事をやっている自分に飽きてしまって、仕事も低空飛行だったんです。でも「ティール組織」の本に出会えたおかげで、私も畠中も「人と組織の探求」にのめり込んでいき、そこから「良い関係づくり」に資する新しいアプローチを得ることができました。
畠中氏 そういう意味では、自分は、ずっと「人と組織の探求」をやり続けている人間だという自己認識があります。価値観・信念・観念が一人ひとり違う中で、集団として大切なものをどう共有するか。それを語り出すと、合宿でもしないと時間が足りないぐらいです(笑)。
藤巻 本当ですね。ここまでお話を聞かせていただいて、コーポレートブランディングとは自社の歴史に埋もれている価値を掘り起こし、そこに新たな解釈を加えながら未来に向けて可視化させていく取り組みであると改めて実感しました。社員のみなさんに新しいパーパスやビジョンを浸透させていくことは決して簡単なことではありませんが、そこでブレずに一貫性のある活動と発信を経営層から続けてこられて、それが結果的にクライアントからの期待値向上にまでつながっているところが、素晴らしいと思います。これからの10年、どんな進化をされるのか、ワクワクしています。有益なお話をお聞かせいただき、ありがとうございました。
